Eje(c)t
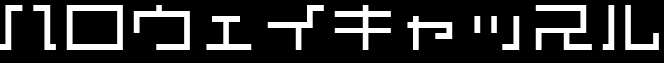  |
| <概要> 全世界8700万のspringファンの皆様、お待たせしました! 遂に世界的ネットアイドル、springの脳に接続する時が来たのです! 彼女の脳に創造された世界、ハロウェイ・キャッスルは危険な罠が張り巡らされた危険なお城! 悪い魔法使いにこの城に閉じ込められたspringは、あなたの助けを待ちわびています。彼女の下へたどり着けるプレイヤーは先着五〇〇名のみ! 選ばれし五百人の王子達だけが限定コンサートへのチケットを手に入れる事が出来るのです。 あなたのspringへの想いは、張り巡らされた数々の罠を退け、見事彼女のもとに届くのか!?
それではspringの世界観が反映されたファンタジーワールドを、存分にお楽しみください。 now loading......... now loading............ now loading........... |
踏みしめたタイル張りの床は、一面血の海だった。
ゲームワールドに降り立った途端、むせかえるような奇妙な匂いがガスマスク越しに漂ってきて、思わずこみ上げた吐き気に口元を押さえた。辺りを見渡すと、そこは茶目っ気たっぷにおどろおどろしく装飾された、洋風のロビーだった。
「なんだよこれ――」
色とりどりのポップなキャンディーやハロウィンに見るようなジャックオーランタン、きらびやかなシャンデリアに、不安定な光を揺らすキャンドルスタンド。ゴシック調の世界観だ。いかにも女の子が好きそうなデザインだった。
そこに、ごろごろと死体が転がっている。かわいらしいデフォルメされたキャラクターにまみれて血を流すその姿は、現実の生々しい人間の姿そのもので、空想の世界に突然ぶちまけられた現実(リアル)のようだった。死体がはき出す血はロビーを一面黒々と染め、黒瀬の足下まで濡らしている。先ほどから鼻腔にへばりつくこの奇妙な匂いは、血の臭いだったのだ。息が詰まる。
『アウターホリッカーによる改変ですね』
コーディがふわりと姿を現した。彼女はとんがり帽子に黒いローブ、それにやけに丈の短いティアードスカートとタイツにブーツと、ふざけているとしか思えない魔法使いを意識した格好をしていた。何か苦言を呈しようと思ったが、死臭のすさまじさに口を開くのがためらわれた。
『1プレイ580円で複数回挑戦して遊ぶタイプのアイドルファンのためのゲームだったようです。城の頂上までたどり着けば、そこでお姫様に扮したアイドルと出会ってゲームクリアという形式のようですが』
彼女は至極冷静な顔で転がっている死体に目を落とす。
『こういった過剰な演出は本来意図されたものではありません。ホスト元のアウターホリッカーにより、改変されたものです』
黒瀬はマスクの下で目を白黒させてから、いらだたしげに
「何言ってるかわけがわかんないだよ! くそ、また無理矢理連れてきやがって――――」
『無理矢理ではありません。そのマスクをかぶった時、あなたは排出者(イジェクター)となることに了解したはずです』
む……と黒瀬は口ごもった。確かに、言われてみれば、そんな記憶もあった。だがあの時はあの時だ。選択の余地はなかったし、血がのぼっていた。眞子を助けなければと必死だったのだ。黒瀬は足下にあった死体をいらだたし気に足で蹴りやり
「だいたい、なんで俺が見ず知らずの他人を助けなきゃいけないんだよ。勝手に悩んで、自殺しようとする奴なんか、死なせてやればいいんだ……」
ぶちぶちと文句を吐き連ねる黒瀬の前に、音もなくコーディが回り込んできた。エメラルドグリーンの透けるような色が、黒瀬の目を射貫く。まるで胸の奥にまでその視線が入ってくるように感じて、黒瀬は思わず口をへの字にして黙り込んだ。
『他の誰にもできるなら、誰かが手をさしのべるのを期待して、じっと待てばいいでしょう。ですが、外側中毒は違います。どんなに願っても、どんな犠牲を払っても、他の誰にも彼らを救う事はできない』
左手に、ひんやりとした心地よい冷たさが宿った。コーディが身を寄せて、その細い指で黒瀬の手をとったのだ。
『あなたにしか救えない。だから、救わなくてはいけない。それがあなたの権利であり義務なんです』
黙りこくった黒瀬は、文句の一つでも言いたげな不満げな表情で彼女を見つめ返した。コーディは少しも目を逸らすことなく、まさに機械じみたまっすぐさで黒瀬の瞳を見つめ続ける。しばらくすると、黒瀬は気まずそうに表情を歪め、視線を明後日の方へ逸らした。
まったく、人工知能(AI)というのは厄介だ。機械だから妥協する事を知らないし、にらみ合っても根負けしたりしない。争うだけ、無駄だ、これは――――
「……さっき、ホストがどうとか言ってたよな」
コーディの手を振り払った黒瀬が、辺りを見渡しながらそう言った。背を向けた黒瀬は知りえない事だが、コーディは振り払われた手を、取り残された子供のように宙を漂わせ、それから、反対の手の中にゆっくりと納めた。
『ホストとはゲームを主導的に運用する脳を指しています。Play fun!12は脳の機能をパッシブにもアクティブにも利用して作用していますが、脳で創造した世界を公開する際、Play fun!12は脳を外部の接続者に解放して要求された情報を処理して――』
「わかりやすく説明できないのかよ、お前」
『……つまり、ここはアウターホリッカーの頭の中に作られた世界で、この世界をどうするのかは、全てアウターホリッカーにゆだねられているという事です』
うなるように、黒瀬は鼻を鳴らした。今や自分達はアウターホリッカーの手の内――脳の内にあるという事か。
『……どうやら本ゲームのアウターホリッカーはホスト元であるspring本人のようですね』
辺りの死体を足蹴にして調べていた黒瀬は、いぶかしげにコーディに目を向け、
「springって……アイドルだろ?」
ゲーム前のブリーフィング画面(突然出てきて驚いたが、つまりあれは簡単な説明書みたいなものなのだろう)ではそう書かれていたように思う。
『そうですが、それがなにか?』
コーディは至極当然のようにそう言った。「いや、べつにさ……」と黒瀬は口ごもる。だが、彼女の言説に寄れば、アウターホリックというのは『無意識の自殺』ではなかったか。黒瀬の中では、昼の世界で燦然と輝き華々しく活躍するアイドルと、自殺というのは、どうも結びつかない。
『どんな人間にも、死の可能性は開かれていますから』
コーディは辺りを漂いながら、死体を見下ろして言う。
『そのリセット(死)スイッチに気づいてしまうと、ダメなのです。目を逸らそうとしても、ずっと頭にちらついて。そのうちスイッチを押したい衝動が、無意識に有意識を浸食していく。もっとも、そのスイッチはリセットなんてものではなく、再起動も許されない電源スイッチで、救いを求めて押したのに、希望を抱いたまま死――――』
不意に、彼女は振り返った。
『すみません。変な話をしています、私』
そう言われて、自分が彼女の言葉に聞き入っていたのに黒瀬は気づいた。あぁ、うん……と曖昧に言葉を濁す。彼女が語る言葉には、妙に――――妙に"実感がこもっていた"気がした。
だけど、"実感"って?
彼女は祖父の屋敷の地下に広がった機械が作り出した疑似人格(AI)だったはずだ。祖父との暮らしは酷く非機械的(ローテク)だったので機械には詳しくないけれど……最近の人工知能(AI)は死について考えを巡らせたりするのか?
『彼女に興味があるのでしたら調べておきます』
「いや、別に……興味はないけど」
大したことじゃないですから。彼女はそう言って、何かウィンドウを取り出して操作する 。それから、ついでのように黒瀬に目を向け、『本ゲームの終了条件ですが』と話す。
『本ゲームの目的はspring――つまりアウターホリッカーの元へたどり着く事です。彼女の元にたどり着いた時点でゲームクリアとなり、ゲームは終了します。逆にアウターホリッカーにとってはそれがゲームオーバー条件となり、排出(イジェクト)となるわけです』
「アイドルの所へ行けばいいだけ? 行くだけでいいのか?」
黒瀬はほっと息をついた。気負っていた気持ちがすっと楽になる。眞子の時みたいな、あんな殺し合いみたいな真似をしなくていいなら、楽勝だ。
『でも、油断しないでくださいね。この様子じゃ――』
「わかってるよ」
黒瀬はさっと手を振ってコーディの小言を追い払った。今朝のスウィートスモークの件といい、いちいち細かい事にうるさい。彼女が言いたい事くらいわかっている。この辺りに転がる死体の異様さを警戒しろといいたいのだ。
ある日突然脳に住み着いた奴に、あれこれ指図されたくなかった。祖父が言うならまだしも。何も知らないくせに……。無表情顔でじっとこちらを見つめるコーディを横目に、黒瀬は手近な死体に歩み寄った。
足で、その体を仰向けに転がす。
目を細めた。
みぞおちから腹へかけて、切り裂いたような大穴が開いていた。ぬらぬらと光る血にまみれて内蔵が垣間見える。どんな事をしたらこんな傷がつくんだ? 何かとてつもなく巨大な、鋭く太い何かで一突きされたみたいな……
『横に避けてッ!!』
コーディが突然叫んだ。
死体に気を取られていた黒瀬はその声にとっさに反応できず、思わず振り返ろうとして、しかし体が突然意思に反して横っ飛びした。背中を打ち付けて息が詰まる。倒れこんだ目の前で、さっきまで自分が突っ立っていた空間を、突然横薙ぎに何か巨大な影が横切って、壁に突っ込んだ。唖然として見ると、壁に突き刺さっているのは鎖で天井と結ばれた巨大な鎌で、それが土煙に包まれてぎらぎらと刃を輝かせている。
「な、なんだよ、こ――――」
『天井!!』
今度はコーディの声にとっさに反応できた。シュッという音と共に何か影が頭上で素早く動いたのを見て、黒瀬は即座に体をひねって転がる。直後、黒瀬の肩をかすめて凄まじい質量をともなった鉄球の一撃が床を粉砕した。渇きかけていた粘着質な血がぶばっと音を立てて飛び散り、タイルの破片が黒瀬に降りかかる。転がっていた死体の顔面が鉄球に叩き潰され、破裂した頭蓋の破片が血と粉塵の中に乱れ飛んだ。
だがそれを見て驚いている余裕はなかった。薄い金属プレートの束がこすれ合うような音が耳元でしたと思ったら、騎士甲冑が頭上で剣を振りかざしているのが見えた。どこから出てきたなど考える前に、体をひねった。迫り来る剣の先端。腰を無茶苦茶にひねって体を回転させると、左手を床について軸にし、思いっきり右足を突き出した。剣は黒瀬のガスマスクを破って頬を切り裂いて床に突き刺さり、彼の放った突き蹴りは見事甲冑の兜をとらえる。だが手応えはまるで無かった。兜はあっさり吹き飛び、甲冑は突然意志を失ったみたいにふらふらと後ずさりして倒れた。
尻餅をついて、息を荒くする。甲冑の中身は空っぽだった。不意にゲームを始める前に見たブリーフィング画面を思い出す。
――――ハロウェイ・キャッスルは、危険な罠が張り巡らされた危険なお城!――――
息をするのにも慎重になった。辺りを見渡す。壁に並んだ蜂の巣のような小さな穴の群れ。脈絡無く床に設けられた網で覆われた排気口。壁際に立ち並ぶ甲冑。ビロードの絨毯に覆われた、かすかにへこんでいる床。目につくもの全てが疑わしく感じて、額に冷たい汗が流れた。
『罠はプレイヤーを凄惨に殺害する目的で設置されているようです』
眼前に滑り込んできた、華奢な細い手。差し出され彼女の腕は、トレンチコートが派手に裂かれて、白い腕の合間に流れ出した血が見え隠れしていた。
思わず彼女の顔を見上げる。無表情顔の中で、碧い瞳が静かに自分を見つめていた。思わず、言葉が口をつく。
「怪我したのか!?」
あまりに勢い込んで聞いたからだろうか、コーディはきょとんとして、それから『あぁ』と無感動そうにつぶやいた。
『クロセさんを押した時に、あの鎌に切られたようですね』
彼女は手をかざして、無数の文字列が並ぶ幾多のウィンドウを宙に出現させると、ウィンドウの中の数字を撫ぜるようにして書き換えた。すると、腕の傷はみるみる内に消え去り、トレンチコートの破れもあっという間にふさがった。
『私はいいんです。データですから、数値を書き換えれば元に戻せます。けど、クロセさんはそうはいきませんから』
彼女はそう言って、また手を差し出した。
黒瀬はその手をじっと見つめた。
『……何か?』
平坦な声でそう問われて、口にしかかった言葉を飲み込んだ。黙って彼女の手を掴み、立ち上がる。
『本来は電気ショックや煙が出る程度な罠のはずですが、ホストが――』
辺りを見渡してそう言う彼女に、黒瀬は頭をかき、
「……springとかいう女がやったのか。イカれてんな」
『私が先行してマップの罠(スクリプト)を確認しますから、気をつけてついてきてください』
そう言って、彼女が宙に浮いて先に行くのを、黒瀬は一瞬歯がゆそうな表情で見送った。それからまた一瞬だけ視線をそらし、顔を上げると、足下に転がっていた剣を手にとる。
「待てよ」
コーディの背に追いつくと、彼女の体を自分の背に押しやって、先頭に立って歩き出した。剣を使って怪しそうな箇所をこづきながら、非効率にもゆっくりと歩み出した彼の脊を、コーディは薄い唇を微かにひらいて、虚を突かれたように見送っていたが、結局何も言わずに、素直に後についた。
そうして誰もいなくなったロビーで、死体の一つがゆっくりと身を起こした。黒瀬達が消えた階段に目を向けると、それは静かに後に続く。
慎重な歩みは、本来十分もかからずにクリアできるはずの簡単なステージに、四十分もの時間を浪費させた。
焦る気持ちを抑え、死体の群れを踏みしめて一歩一歩階段を昇っていくのは随分神経を使った。コーディの指摘する罠の位置とその対応方法は的確だったが、時折マップに記載されていない罠が仕掛けられている事もあり、黒瀬自信も観察眼をゆるめるわけに行かなかった。それに、実際に罠を回避するのは黒瀬の運動能力にかかっている。一歩でも足の置き場を間違えれば、一度でも手を滑らせれば、剣山に突き刺さったり、せり出す壁に押しつぶされた死体と同じ道を歩む事になる。
『おそらく、これがゴールですね』
集中力が襤褸切れみたいになった黒瀬と、汗一つかいていないが僅かに眉根を寄せたコーディが、ようやくたどり着いたのは、見上げる程巨大な木枠の扉だった。ちょうどおとぎ話なんかに出てくるお城の扉のようだ。胸の高さ程の所に、べたべたと手の跡がつけられていて、黒瀬がなんだと思ってよく目をこらすと、乾いた血だった。
「……ここをくぐれば、ゲームクリアなんだよな」
『そのはずです』と、コーディは並べ立てたタスクウィンドウにエメラルドの瞳をさっと通しながら言った。
『罠は確認されませんでした。進めます』
黒瀬はうなずき、扉を押し開いた。
室内はのっぺりとした暗闇に飲まれていた。光の一切は拒絶され、足を踏み出す床すら見えない。踏み入るのはためらわれたが、時間がない。ゆっくりと暗闇の中に潜り込んでいく。
唐突に背後の扉がきしむがした。二十歩も歩いた頃だった。慌てて振り返るが既に扉は完全に閉まった後だ。
「なんだ――扉が閉まった!」
『解析しています……施錠されたようです。部屋に入った時点でスクリプトが作動しました』
黒瀬は扉に駆け寄って拳を叩きつけたが、ぴくりともしなかった。鈍い音が暗闇に響くばかりだった。辺りを見渡し、歯噛みする。わかりきっているが、現実をもう一度確認する。
「閉じ込められた?」
『わかりません、事態を把握するまで動かないのを推奨』
彼女がタスクウィンドウをいくつも起動させて、凄まじい速さでそれを操作し始めた。黒瀬はぎゅっと剣を構える。口の中が緊張で乾いているのに気づく。生唾を飲み込んで、腹をくくろうとする。だがエントランスで襲ってきた罠を思うと、ぞっとした。血みどろの死体、必要以上にまき散らされた鮮血や肉片―――今思えば、あれには偏執的な、狂気じみた"歓喜"を感じさせた。人をばらばらにするのに、ここの"主(あるじ)"は、快感を感じていたのだ――――
辺りは完全に真っ暗闇だった。ここで罠が襲いかかってきたとしたら――――音だけを頼りに、避けられる自信はない。マスクの中の、自分の呼吸が、緊張しはじめた鼓動に合わせ、荒くなっていく。
突然、照明が灯った。
はっとして眼を向ける。真っ白な人工灯がぽつんと暗闇に落とされ、その光に包まれて、一人の少女が地面にへたり込んでいる。
「っぅ……ぅぅ、っ、うぅ……」
低い声で呻いている――いや、嗚咽を上げている。
フリルのたっぷりついた、ピンクと白を基調にしたポップなロリータ調のドレス、それによく熟れたチェリーみたいな色の髪飾り、肌は白く艶めかしく、人間というよりはゴテゴテとデコレーションされた過度に甘いケーキのようだ。ブロンドの髪が、真っ白な照明に照らされて煌めいているが、よく手入れされているつやのある髪は、酷くかきむしったみたいに乱れていた。
暗闇に光が灯った事で、黒瀬はようやく周囲の状況がかすかに把握できた。ここはまるで死体置き場だ。ここまで来るまでに見た死体など物の数ではない。床一面が死体に覆われ、女の背後には積み重なった死体で山ができていた。彼女はその死体の絨毯をかき抱くように地面にべったりと張り付いて涙を流している。低く、低く、嗚咽を暗闇に這わせる。
「……す、springか、お前」
かすれた声はうわずっていた。返事はない。……よく見ると、彼女はその手になにか、人形を握っている。薄汚れた、何か――――荒い毛糸で出来た人形のようだった。その首に巻かれているモノに気づいた時、黒瀬は知らず、生唾を飲み込んだ。荒縄だった。首をくくるように巻き付けられた縄が、springの手から人形の首へと繋がっている。彼女の口元が、人形の耳に寄せられ、小さな声で何か囁いている。
『――――歌っています』
「は? 歌?」
コーディは歌詞をそらんじるようにつぶやく。
『………おねえちゃん……?』
黒瀬がいぶかしげに眼を細める。彼女は微かな声から断片的に下したらしい判断を述べた。
『誕生日をお祝いしているようです。彼女の、おねえちゃんの』
思わず、頬がひきつった。おねえちゃんって誰だ? いや、彼女はあの薄汚い人形に囁いているのだから、まさか彼女にとってはあの人形が『おねえちゃん』なのか? わけがわからない。理解不能だった。死体の山に囲まれて、世界的アイドルが、お人形と一緒にお祝いとは――――思わず、一歩下がる。
その時、背後から扉が勢いよく開かれる音がした。
「spring!」
血みどろになった男が、足下をおぼつかせながら、部屋に飛び込んでくる。突然現れた別のプレイヤーの存在に、思わずあっけにとられた。男は手にしていた金属バットを――武器代わりに使っていたのだろうか――投げ捨て、嗚咽を上げる女に駆け寄った。
「助けに来たよ! よかった、無事だったんだね……!」
男はちらちらと黒瀬を見ながらそう言った。私たちの後をつけていたようです、とコーディが囁く。どうやら、こちらを試金石にして罠の回避法を探っていたようだ。どこにでも狡猾な奴はいるものだ。
「バカかお前、そいつから離れろ!」
男は黒瀬に眼を向けると、いやらしい、勝ち誇った笑みを浮かべて言った。
「僕が一番だよ。一番に部屋に入ったからって油断したね。でもダメだよ。springを一番最初に助けたのは僕なんだ。僕が彼女の王」
言葉はそこで唐突に途切れた。彼の背後でエンジンがうなり声をあげ、続く声をかき消してしまったのだ。男が振り返ろうとした瞬間、そのみぞおちから突然血と肉が吹き出した。凄まじい金切り音が血肉の間からがなり立てる。断末魔の悲鳴があがったが、全てかき消されてしまった。彼は倒れ、足下に転がる無数の死体の仲間入りを果たした。そしてその背後から、血みどろになったデコレーションケーキみたいな女が、両手で抱えた自分の身の丈程もありそうなチェーンソーから血をほとばしらせながら姿を現す。
「ぅぅ、ううう、うううううううううううう――――ーッ!!!!」
顔を上げた彼女の顔には、鉄仮面が被さっていた。悲しげに目を下げた仮面(ペルソナ)。苦悶の声がその下から漏れる。
「ぅぅぅううるさいうるさいうるさいぃぃぃぃぃ――――!! おねえ、ちゃん――――おねぇ、ちゃ――――」
「こ、こいつ……!」
黒瀬は思わず後ずさる。その彼に向けて、女はチェーンソーを振り回し、血と肉を一直線にまき散らした。思わず腕で防いだ黒瀬のマスクに、赤い血がべったりとへばりつく。ガスマスクの下、毒づいて、
「何がお姫様だよクソ――――これでクリアなんだよな、そうだよな!?」
傍らで、ウィンドウを高速で処理していたコーディの手元に、甲高いビープ音と共に真っ赤なウィンドウが滑り込んでくる。彼女ははっと息をのんで、瞳を真っ赤に染め上げた。
『クリア条件が書き換えられています』
黒瀬が目を剥き、
「これで終わりじゃないのかよ」
『クリア条件が更新中――――ホストによる改変です!』
コーディが叫び、チェーンソー片手に頭をかきむしる女へと目を向ける。女は頭の中で這いずり回っている虫を掻き出そうとしているかのように、細くしなやかな指を髪の間に突き立てる。
「ぅぅぅぅ――――でてけ――――ぅぅぅぅぅぅぅうでていけえええええええええ――ッ!!」
金切り声を張り上げた、その瞬間。
彼女の背後の暗闇がゆらゆらと揺れ、ゆっくりと、辺りの死体が立ち上がった。愕然として、黒瀬は目を凝らす――――死体は一様に首に荒縄がかけられ、先の見えない闇に覆われた天井からつるされている。手に手に血みどろの包丁や鉈、刀やククリナイフをぶら下げていた。立ち上がる死体の群れが、彼女の背後で波立ち、途端、一斉に襲いかかってきた。凄まじい数だった。圧倒された黒瀬が思わず後ずさった、その時。
「ころせえええええええええええええ――――――!!!!」
真っ赤に染まった目を天へ跳ね上げ、女は喉がはち切れんばかりの叫びをあげた。
一斉に迫り来る、死体の群れ。
「――オーバークロック!」
四方八方から襲いかかってくる死体の群れは、とても回避できるとは思えなかった。超反応を得た黒瀬の視界に、エメラルド色の光線が導くように伸びる。
『光をたどってください!』
コーディが指し示す回避ルートを辿って凶器の群れをかいくぐる。濃密な三秒間で、なんとか動く死体の群れから逃れるも、オーバークロックの効果はそれで切れてしまった。荒い息を吐きながら辺りを見渡すと、天井から次々と襲いかかる蛇のようにのたくった荒縄が降り注ぎ、死体の首に絡みついている。首を締め上げられた死体が、力ない体で武器を握り、真っ赤に染まった目をかっぴらく。
「くそ、バカかよ俺は――オーバークロック(切り札)をもう使っちまった! ――クリア条件は!? どうすればあいつをゲームオーバーにできる」
コーディは周囲を幾重にも重なったタスクウィンドウに取り囲まれていた。色濃いエメラルドのタスクウィンドウは、何かのログデータを濁流のような凄まじい速度で更新していく。
『リアルタイムで今書き換えられています。現在のクリア条件は"敵の攻撃に1時間耐える"』
「一時間……!?」
じりじりとにじりよってくる死体の群れと対峙して、黒瀬は冷や汗を垂らす。最初に飛びかかってきた奴と相打ちになる覚悟で剣を構える。
『そもそもアウターホリッカーが死亡するまで5分もありません。不可能なクリア条件であなたと接続しているプレイヤーを巻き込んで自殺する気です』
コーディはさっとspringへ目をやって、微かに唇を噛みしめる。
『クリア条件そのものが罠だったんだ』
「わかってるならなんとか――――」
その瞬間、彼女の横顔の向こうから、ナイフを手に人影が飛び出して来たのが見えた。
「どけ!」
はっとしてコーディを突き飛ばし、剣を影の方へ向ける。あっと声をあげて倒れるコーディ。入れ替わりに、迫り来る死体の姿。コードがぎっしり巻き付けられた鋭いパラシュートナイフが、獣のように飛びかかってきた死体の手に握られている。命の危険を察知した体が電撃のような指令を腕に飛ばし、黒瀬は本能的に手にした剣を突き出した。
手応え。
だが敵は平気な顔をして、そのままナイフごとのしかかってきた。突進の勢いが凄まじく、押し倒される。もみくちゃになり、思わず悲鳴のような怒声をはき出す。
こいつ、不死身か!?
ほとばしる血、敵の体の向こうに突き抜けたはずの剣の切っ先を目にして、黒瀬は戦慄した。幸い体は貧相で小さかったので、なんとか突き放し、蹴り飛ばした。だが吹き飛んだ死体は再び身を起こすと、ナイフを拾い上げる。少しも痛がる様子はない。
再び飛びかかってくる影に向けて、半狂乱になって黒瀬は剣を振り抜いた。だが刃は敵の体を捉えず、その頭上を通り過ぎただけだった。
『クロセさん!』
傍らで立ち上がりかけたコーディの悲痛な叫び。あっと思った。刺される。頭の中が真っ赤な緊急警報で一杯になった。首筋を切り裂くナイフ、噴き出した血が自分の視界を真っ赤に染める――――死の瞬間が、鮮明に脳裏を駆け巡る。
だが、唐突に死体は憑き物が落ちたように崩れ落ちた。
跳ね上がった鼓動、ぜいぜいと息を切らし、震える体。全身が死を覚悟していた。だが眼前では死体がぴくりとも動かず倒れている。見ると、死体の頭上の荒縄が、断ち切られていた。
「これは――――」
『…………あやつり糸(スクリプト)だ』
黒瀬に手を貸しながら立ち上がったコーディは、目の色をかしゃっと黄色に変える。それからエメラルドの瞳を、焦点を合わせる機械レンズみたいに動かした。
彼女は腕を振るい、黄金色に輝くいくつもタスクウィンドウをその眼前に並べた。何事かわからない文字列や数列がさっとウィンドウを駆け巡る。
『時間を稼げば、死体はなんとかなるかも』
「時間を稼ぐって――――」
だがその瞬間、死体達は一斉に黒瀬に襲いかかってく来た。とても相手に出来る量じゃない。情けなくも必死に逃げ出した。時間を稼げだって? そう簡単にやれるものか。毒づきながら、背後に迫る敵の気配に追い立てられるように駆ける。死体達はまるで獣のように四つん這いでその背に肉薄する。その速さは獲物を追い詰める野犬のそれで、すぐさま取り囲まれてしまう。
宙に浮いて横を併走するコーディに、息を切らしながら叫ぶ。
「このままじゃやられる!」
『分かっています。もう少し待ってください』
胸の奥からわき上がる熱っぽい息を、毒づきに変えて吐き出そうとした、
その瞬間
右肩に、突然の衝撃。
肩に弾ける痛みの熱、頬に飛び散った生暖かい液体の感触。喉の奥から、かは、と予期しない空気が押し出された。腕と胸の間に差し挟まれた冷たく鋭い異物の感触に、右腕が震える。
「――――ぁあああッ!」
『クロセさん!』
コーディがはっと悲鳴のような声を上げた。痛みに、思わず黒瀬の足が止まる。だが飛んでいきそうだった理性は、なんとかつなぎ止める事ができた。すぐにでも襲ってきそうな死体達に剣を向け、牽制する。死体達は手にした武器を揺らしながら、黒瀬の周囲を取り囲み始めた。歯を食いしばりながら肩口を見ると、滑らかな流線型のスローイングナイフが、ぬらぬらとした赤黒い血に染まりながら、突き出していた。
「あはははははははは! はは、あははは、ははははははははははははは!!!!」
下品な笑い声を上げるsprigの顔は、いつの間にか笑い顔のペルソナが張り付いている。彼女は死体達に黒瀬を追わせて、舞い踊るようにくるくると回っている。照明の光で、金糸のような髪がきらきらと輝いていた。
彼女を映していた視界が霞みはじめる。失血と、走り回ったせいで、頭に酸素が回っていない。痛みで意識が朦朧としだす。熱の塊が、荒い呼吸となって口から飛び出していく。
「…………コーディ」
思ったよりもずっと弱々しい声だった。拳を額に当てて意識をはっきりさせようとするが、視界はにじんだままだった。奥歯を噛みしめる。コーディはいつもの無表情顔に隠しきれない焦りをにじませて、
『位相電位を切り替えています、すぐに痛みを抑制するための――』
「やれるんだな」
コーディに目をやった黒瀬は、痛みと死の恐怖に染まりながらも、腹をくくった表情をしていた。彼女ははっとして、それから、力強く頷いた。
今にも前のめりに倒れ込みそうな体を、持ち上げる。取り落としそうになる剣を、もう一度握り直す。ぎちぎちと力をこめた拳に、肩口からわき水のように流れ出す血がしたたった。死体達は手負いの獲物に迫る狼の群れのごとく、じりじりと迫る。
「来いッ!!」
剣を身構えた黒瀬は腹の底からそう叫んだ。コーディに賭けるしかない――――何をしてもいい、最後の瞬間まで立ち続けるのだ。彼女の時間を、稼ぐ。黒瀬の背後で、コーディは無数のタスクウィンドウの群れを操っていた。
獣の咆吼が上がる。
一番最初に襲いかかってきたのは、背後からだった。背中に飛びかかってきた死体を、振り向きざまに、斬る――血しぶきと共に枯れ木みたいに死体の首がへし折れ、横薙ぎに吹き飛ぶ。だがその背中を、ククリナイフを振りかぶった別の死体に襲われる。背中に衝撃が打ち付けられ、思わず息が詰まった。直後に激痛が走り、喉から自分のものとは思えない悲鳴が溢れる。熱く灼けた本能で体をひねり、振り返りざま背後の死体の顎を肘で打つ。腐った首は脆くも吹き飛んだが、だくだくと背中から流れる熱い血も見えた。ククリナイフが刺さったのだ。膝をついてしまう。
『正面です!』
コーディの声になんとか反応する。日本刀を振りかざした男が突進してくる。肉薄した瞬間、地面を蹴って男の腕の下に潜り込むと、剣の柄で顎を打ち上げる。そのまま肩を使って死体を体の後方へ転がすと、更に次の死体が迫っている。息つく暇もない――――
眼前に迫る、金属バットを振りかざすその死体の姿は、今しがたspringに真っ二つにされた男の姿。剣を構えようとするが、間に合わない。
バッドが頭蓋に炸裂した。
一瞬目の前が真っ白になり、首がもぎ取られたみたいな衝撃に襲われた。そして直後にずくずくと脈打つような鈍痛が頭蓋内を蹂躙する。全身から力が抜けた。倒れ込みそうになったが、もはや意思の力ではなく、危険を察知した本能が体を制御してなんとか姿勢を保った。
「ぼくがああああああああああああああ!!」
とどめを刺そうと男がバッドを振りかぶって襲いかかってくる。ふらつく足下、混濁した意識と生気が抜け落ちそうな目。それでも黒瀬は剣をまっすぐに構えた。男の突進と、スウィングに合わせて、一瞬の集中力で待ち構えると、カウンターで剣を突き出した。
眼球を突き破り、肉を引き裂いて、力任せにねじ込む感触。
男の目に、剣先が沈み込み、首がへし折れた。眼窩から吹き出す鮮血。その体は後方へ思いっきり突き出され、巨人にはたかれたように後方へ吹き飛んだ。
がんがんと痛む頭を押さえると、滑った血がグローブ越しにぐじゅっと音を立てた。息を荒くし、襲い来る吐き気と激痛を必死に耐える。辺りを見渡すと、次々と首に荒縄のかかった死体が身を起こしていた。とても戦える数じゃない。絶望感で膝をつきそうになる。
『ホストの一部を制圧完了! 糸(スクリプト)を切断!!』
コーディの声がした。
宙に浮いた彼女がさっと腕を振るうと、死体の首に巻き付いていた縄が音を立てて引きちぎれ、死体達ははばらばらと崩れ落ちる。ゆらゆらと周囲を取り囲んでいた血みどろの影が、音を立てて死体に戻っていった。ふらつき、朦朧とする意識の中で、やったと思った
その瞬間
「あはははははははははは――――――!!!!」
凶器じみた笑い声が迫ってきた。はっと眼を向けると、チェーンソーを振りかぶったspringが、凄まじい跳躍でこちらに肉薄してくるのが見えた。攻撃も防御も間に合わない。とっさに地面を蹴って転がると、そのすぐ頭上を、回転する無数の刃とエンジン音がかすめていく。受け身を撮って身を起こすが、すぐにspringはチェーンソーを黒瀬の頭蓋へと振り下ろしてきた。
「くぉッ!!」
もはや本能で黒瀬は剣を両手でチェーンソーへとつきだした。金属と金属が猛速でこすれ合う金切り音が鼻先で悲鳴を上げる。火花が散って、視界を真っ赤に染めた。
「死んで! 死ねよ! 私と一緒に、死ねぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ――――!!」
とても女の細腕とは思えない力でぐいぐいとチェーンソーを押しつけられる。このままでは押し負ける。乱暴な攻撃でがら空きとなっている彼女の足下に気づくと、渾身の力を込めてフロントキックを叩きつけた。
「あぅッ!?」
springがたたらを踏んで後ずさる。その隙を突いて距離を取り、肩で荒々しい息をする。
『失血で身体機能40%低下!』
コーディに言われて、肩を覆う重たい熱のような感覚に気がついた。手をやると、肩口から首に近い部分からだくだくと血が吹き出しているのが分かった。途端、ぐらっと視界が揺らぎ、黒瀬は慌てて頭を振って、なんとか意識を保つ。
『クリア条件は修正できましたが"ホストを倒す"にしか設定できません! 彼女を倒さないと――――あと40秒しかない!』
大量の出血が黒瀬の意思を根こそぎ奪おうとしていた。向かいに立つspringは目のつり上がった鉄仮面の下でいきり立っている。チェーンソーの紐を引いて高らかにエンジンを響かせた。黒瀬は何とか応じようと剣を構えようとするが、激しい打ち合いでブレードがすっかり削れてしまったそれは、とても役に立ちそうになかった。もうろうとする意識の中で代わりになりそうなものはないか辺りを見渡したが、手が届きそうな範囲で見つかったのは、あの引き裂かれた哀れな男が投げ捨てた金属バットくらいしかない。
「うがああああああああああああああ!! がぁ、あああ、あああああああああああああ!!!! 首を、よこせええええええええええええええええ!!!!」
springが跳躍した。迫り来る彼女を視界に捕らえた黒瀬だったが、意識が朦朧として体の動きはひどく鈍い。まるで逆にオーバークロックを使われたようだった。それでも意思だけは明確にspringを倒すことに集中していた。地獄の底にたらされた一本のクモの糸を手繰り寄せるように、足元に転がっていた金属バットを足で蹴り上げた。空中でひっつかみ、バッティングの要領で思いっきり振りかぶる。手を伸ばせば触れられそうな距離まで肉薄したsprigに狙いを定め、まず振りあげた足を下ろし、勢いそのままに腰をひねり、全身のばねを存分に使って全力で振りぬいた。耳を覆いたくなるような甲高い音がして、硬い手応えが腕に伝わった。直後、ばらばらに吹き飛んだチェーンソーの破片が黒瀬の全身に突き刺さる。のしかかるように体ごと突っ込んできたspringに押し倒され、全身を襲う激痛にまみれながら、倒れこんだ。
訳もなく寒さを感じて、ぶるぶると体が震えた。それなのに、引き裂かれた傷口だけはじんじんと火を吹いているみたいに熱を帯びているのだ。自分の体が自分のものでないような、霞がかった感覚に包まれる。コーディが呼んでいる声がした。叫んでいる――おきなきゃ、そう思った。手足を動かすとガラスがちくちくと突き刺さるような痛みが走る。血を吐きながら何とか体を起こすと、眼前で何度も顔面を床にたたきつけているspringに気づいた。
「あああああああああ、見ないで、見るな、あぁ、誰も、私を、見るなぁああああああ……」
彼女のかたわらには、粉々に砕け散ったペルソナの破片があった。チェーンソーの破片が彼女の仮面を砕いたようだった。何度も何度も顔を床に打ち付ける彼女にふらつきながら歩み寄ると、顔を掴み上げた。染みもシワもニキビもない、雪原みたいな肌をした整った顔が、呆然と黒瀬を見上げている。碧いアーモンド型の目をのぞき込むと、感じるモノがあった。それは違和感でもあったし、やはりという失望でもあった。
かすれる声で、つぶやく。
「お前、正気だろ」
springは応えなかった。彼女の狂気にまみれた瞳が、言葉に反応して揺れ動くのがわかった。
やっぱり、そうか――黒瀬は奥歯を噛みしめる。
「……くそ、頭が痛ぇ……気が狂った振りをしなきゃ、"昼の世界"で生きられないのかよ」
黒瀬は荒い息を吐き捨て、顔にへばりつくガスマスクをはぎ取った。素顔で彼女の目をのぞき込むと、その奥が不安定に律動しているのが分かった。喉の奥で毒づく。その瞳の動きだけで分かった。こいつは不安定で、恐がりで、いつも無理をしていて、世界の大きさと無情さにちっぽけな自分が耐えられなくなる日を恐れている。
吐き捨てる。
「一緒だ、こいつ――――」
傍らに浮いていたコーディがエメラルドの瞳をさっと群青に変えて、黒瀬に目をむける。
額から血を流して、怯えと焦りに顔を歪めていたspringは、黒瀬の言葉に微かに目を見開いた。固く歪んだ表情は柔らかさを取り戻し、きゅっと唇を結んでみせた。
黒瀬はその顔を突き放すと、手にしたバッドを肩にかける。最後の力を振り絞る。
「お前を排出(イジェクト)してやる」
一気に振りかぶり、救いを求める堕天使みたいな彼女の顔に、思いっきり斜めに叩きつけた。確かな手応えと粉砕音と共に、スイカみたいに彼女の頭が破裂して、脳漿と血が辺りにまき散らされる。世界は暗転し、ゲームの電源は落とされる。
「本当に来てくれるなんて……夢にも思わなかった」
そう言って、病室のベッドに横たわった眞子は頬をほころばせた。ベッドの脇に座って彼女を見つめる黒瀬は、何とも言えない、気まずそうな表情をして、視線を落とした。昼下がり、窓からの陽光は真っ白だった光を乳白色に色を変え始めている。照らされた二人に、ゆっくりとした時間が流れている。
前回のイジェクトから三日が経った。世間はあの世界的アイドルのspring(本当に世界的かどうかは疑わしいと黒瀬は思っていたが)がアウターホリックに陥った事、そしてその彼女を颯爽と(当人にとってはとても颯爽とは思えなかったが世間一般では)イジェクターが救った事に、大いに湧いていた。かつてイジェクターが忽然と姿を消してから、もう一年以上経っていた。それが一ヶ月と間が開かないうちに二回も目にできたのだから人々の興奮が天井知らずになるのも無理はない――――とワイドショーで識者とやらが語っていた。空前のイジェクターブームだとも。ニュースから流れるそんな世界の熱狂をよそに、なんだよこれ、と黒瀬は戸惑っていた。まったく当事者の知らない所で当事者でも何でもない奴らがお祭騒ぎを起こしている。イジェクターは最高だ! 彼は本当のヒーローだ! カッコイイ、大好き! ――――そんな声がセルネット中にあふれかえっている。自分はそんなに祭り上げられるような事をしたのだろうか。称えられるような立派な人間だろうか――――実感はまるで湧かない。だが、悪い気はしなかった。果てしなく遠い所にあった現実という世界……『昼の世界』が、向こうから勝手に、ぐっと近づいてきた気がする。いや、それどころか、昼の世界は今や自分を中心に回っているのではないかとすら思う。イジェクターへの賞賛を目にし、耳にする度、黒瀬は言いようのない高揚感を感じていた。
その浮ついた気持ちが、外の世界への恐怖をわずかに和らげた。今日、眞子の元へ足を運んだのもそのためだ。ほんの少し、ほんの少しずつだが、現実に手を伸ばしかけていた。あともう一歩だけ足を踏み出せば、触れられるんじゃないかと思う。現実を変える力が、自分にはあるんじゃないのか……そういう希望が、黒瀬を突き動かす。
「リンゴ、食べますか」
器用にナイフを使ってうさぎ型に切った彼女が黒瀬にそれをさしだした。普通、逆じゃないか。ぼそぼそとそう言うと、「そうですね」とおかしそうにくすくす笑った。もうほぼ全快していて、今は検査のための入院で退屈しているそうだ。
見舞いに現れた黒瀬を、眞子は最初、あっけにとられて見つめているばかりだった。数秒のお見合いの末、気まずそうに黒瀬が口を開くと、彼女は慌てて部屋に引っ込んだ。入ってこないで! 絶対入ってきちゃだめ! と叫ばれてはなす術がない。しばらくの後、おずおずと扉を開けた彼女はほんの少し身なりが整っていた。相部屋の住人が、クスクス笑っていた。
それから彼女はベッドについて、ユビキタス機能で呼び出したキーボードで何やら誰かと連絡を取っていた。黒瀬をちらちら見ながら、「ほんとに来るなんて」とか「どうしよう」とかつぶやいていたが、「元気?」と尋ねると、とてもうれしそうに「はい」と照れ笑いを浮かべた。
「……なんだか、雰囲気が変わりましたよね」
リンゴをかじっていた黒瀬に、眞子がそう語りかけた。彼女は以前よりずっとリラックスしているようだった。イジェクト以来、彼女の方がよっぽど雰囲気が変わったと思う。
「そう」
「うん。なんだか、一緒にいると、前より時間がゆっくりに感じるっていうか……雰囲気が、柔らかくなったっていうか……」
よくわかんないや。結局そう言って、彼女は笑った。その笑顔を見ていると、自分が本当に変わり始めているのではないかと黒瀬は少し胸が高鳴った。あの屋敷の暗い部屋の中で、楽しそうに桜吹雪を見上げる『昼の住人』達を見つめるしかなかった自分が、少しずつ変わり始めている。一体何に変わろうとしているのかはわからない。だが、何かが、変わり始めている。良い兆候なんだと、強く思う。
そう、すべては外側の世界(アウターワールド)のおかげ
「あ――――えぇっと……お兄、ちゃん?」
眞子が言いづらそうにそう声をかけてきた。物思いにふけっていた黒瀬が顔を上げる。
「どうしたの。ずっと触ってるけど……」
そう言って彼女は視線を下げた。彼女の視線を追うと、自分の手が見えた、首からつっている動かない左腕。その手の先を、右の指先が撫でていた。せわしなく、急かすように。「痛いの?」彼女が尋ねて、黒瀬はさっとその手をほどいた。大丈夫。短くそう返事をする。
最近、左手の感覚に違和感があった。
アウターワールドでの経験が、動かない左腕の存在を異物として感じ始めているようだった。日常生活の中でも当たり前のように動かそうとして、動くはずもない現実に気がついてはっとする。足も時々動くのではないかと錯覚して、つまづいてしまう事も多い。それが続いてくると、だんだんと動かない手足にイラ立つ事も多くなっていた。どうして動かないんだ、どうして、なんだよ、この腕、この足――――アウターワールドと、現実のギャップに、戸惑う。
「……さっき、誰と連絡とってたんだ」
話を変えるためにそう言った。眞子は「え?」と目をまん丸にしてから、困ったように眉尻を下げて「えーっとぉー……」と身をすくめた。それから思い切ったように顔を上げ、
「その話なんだけどね、あの、話しておかなくちゃいけない事があって」
勢いよく扉がスライドする音がした。
眞子があっと声を上げ、黒瀬はいぶかしげに振り返る。かっかっかっと小気味よい足音が迫ってくる。病室にそんなに元気に入ってくる奴がいるかとむっとした。文句の一つでもつけてやろうかと思う。だが、部屋に堂々とモデル歩きで入ってきた彼女が、同じ病室の患者達のため息や驚嘆を引き連れて眼前にやってくると、そんな気持ちはまっさらに吹き飛んでしまった。黒瀬の前にむんと胸を張って立った女は、こちらにぐいと顔を寄せ、
「黒瀬、完爾君?」
遺伝子染髪の綺麗なブロンドの髪に、水晶みたいな碧眼、化粧もしてないのに染みもしわもニキビもない雪原みたいな肌、すらりと高い背丈をぐっと黒瀬へ折り曲げ、6:4くらいで綺麗に分けたロングの髪が、見上げる黒瀬の頬をかすめる。柔らかくて甘ったるい、果物みたいな香りが彼女から漂ってきた。血の匂いじゃない。
唖然とした黒瀬は言葉も出なかった。彼の背後で眞子が泣きそうな顔をしていたが、そんな事には気づくよしもなかった。黒瀬の前で、女はにっといたずらに成功した子供みたいに笑った。かすれた声で、ようやく黒瀬が言葉にできたのはたったこれだけだった。
「お、まえ、spring……」
その名を聞いた彼女は、ますますうれしそうに笑みを浮かべた。妖艶な、艶めかしい笑みに転じる。
「お久しぶり――――そうだよね?」
つい三日前、壮絶な闘いを繰り広げた彼女の、その楽しそうな顔に、目を奪われるしかなかった。